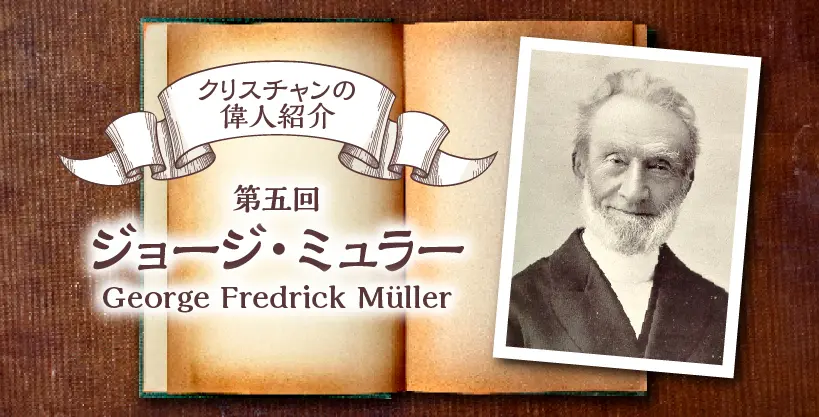
こんにちは、ノイです。
今回ご紹介する偉人は、イギリスの孤児院の創設者ジョージ・ミュラーです。
ミュラーは「神だけにより頼む」ことによって数多くの孤児院を創設し、約1万人の孤児を救済した信仰と祈りの人でした。
また、海外宣教にも尽力し、「世界的大伝道者」とも呼ばれています。
偉大な働きを成したミュラーですが、神に出会うまでは窃盗を繰り返し、投獄された経歴を持ったかなりの問題児でした。
キリストの愛に出会ったミュラーの生涯を思うとき、聖書に約束された「新生」について考えずにはいられません。私たちはミュラーの人生に、神の新しい創造を見ることができるのです。
だれでもキリストにあるならば、その人は新しく造られた者である。
古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。
(コリント人への第二の手紙5章17節)
目次

日本海を見て育つ。 幼い頃、近所の教会のクリスマス会に参加し、キャロルソングが大好きになる。 教会に通うこと彼此20年(でも聖書はいつも新しい)。 好きなことは味覚の旅とイギリスの推理小説を読むこと。
ミュラーは1805年9月27日にプロシア(現在のドイツ)のクロッペンシュタットで生まれました。父親は国税局に勤める役人で、一家は父の仕事の転勤によってプロシア内を度々引っ越しました。
 ミュラーには3つ年上の兄がいましたが、父親はミュラーを偏愛し、弟が生まれてからもそれは変わりませんでした。食事中のマナーが悪くてもミュラーだけは注意されず、兄にいたずらをしても叱られることはありませんでした。
ミュラーには3つ年上の兄がいましたが、父親はミュラーを偏愛し、弟が生まれてからもそれは変わりませんでした。食事中のマナーが悪くてもミュラーだけは注意されず、兄にいたずらをしても叱られることはありませんでした。
父親は、ミュラーが幼い頃から「生涯暮らしに困らないために」安定した地位と収入が約束された国教会の牧師になることを願い、ミュラーをルター派の大聖堂付属の教育学校に入学させますが、聖書に基づいた家庭教育も行っていませんでした。※
放任主義の両親のもと、ミュラーは自由奔放に育ちます。
※残念なことに19世紀のドイツでは国教会が世俗化し、安定した地位と名誉を持つことができるといった理由で子どもを聖職者にしようとするエリート家庭が少なくありませんでした。
ある時から父親は、度重なる引っ越しで友だちができない子どもたちに、その寂しさを紛らわせるようにと過剰なお小遣いを与えるようになります。
同時に、お金の使い方と貯金する習慣を学ばせようと考えたのですが、まだ自制心の育まれていない子どもたちにとって、それは罠となりました。
ミュラーは欲しいと思ったものを我慢することなく手に入れる習慣が身に付いてしまい、成長してからも、良心や理性を踏み倒して欲求を優先することが止められなくなってしまうのです。
ミュラーが7歳の時になった頃には、兄弟の金遣いの荒さは近所で有名になっており、9歳の時には、父親から渡された出納簿の帳尻を合わせるため、父の書斎からお金を盗むほどになっていました。
父親から問い詰められても嘘で言い逃れることを繰り返し、家で預かっていた政府のお金に手を出したこともありました。
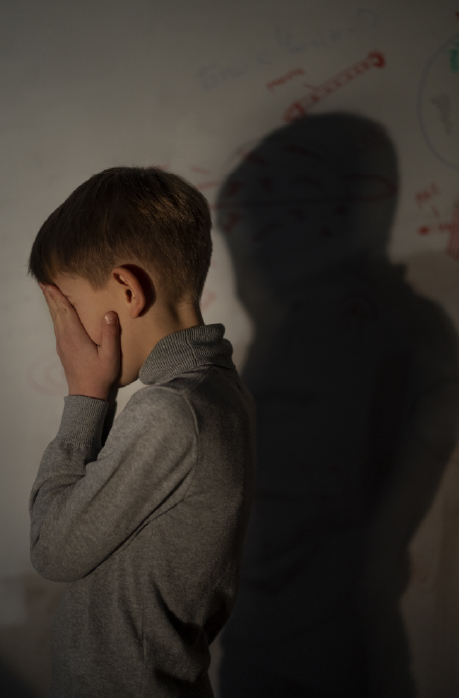 ミュラーの自叙伝には、他人のパンを盗み食いしたことにはじまり、10代前半で盗みと飲酒が常習化していたことが記されています。
ミュラーの自叙伝には、他人のパンを盗み食いしたことにはじまり、10代前半で盗みと飲酒が常習化していたことが記されています。
悪行はエスカレートし、家のタンス貯金から計画的に金銭を盗み、金を得るために親をだますなど、反抗期やいたずらでは済まされない数々の行いを、ミュラーは自身の「罪」として赤裸々な記録を残しています。
母親は心を痛め、父親が厳しく叱ることもありましたが、ミュラーは手が付けられないほどの不良少年になっていました。
ミュラーは14歳のときに母親を亡くしていますが、その日も友だちとカードゲームに興じて酔いつぶれ、翌日に母の訃報を知ったのでした。
15歳のときにミュラーは堅信礼※を受けます。
しかし、それはあくまでも形式上のことで、ミュラーは自叙伝のなかで「神への祈り、真実な悔い改め、信仰、救いの計画への知識は皆無だった」と述懐しています。
※堅信礼:洗礼を受けた信者が信仰を自分の意志で確認し、表明する儀式。
とうとうミュラーは16歳で前科者となります。
だまし取ったお金を旅行で浪費し、高級ホテルで放蕩三昧した挙句、宿泊費の不払いによって逮捕されたのです。父親のおかげで1ヶ月もしないうちに釈放されましたが、この出来事もミュラーの生き方を変えることはできませんでした。
父親はミュラーを更生させるべく、ノルトハウゼン校へ入学させます。
この学校は大学神学部の予科のようなもので、2年半の間、厳しく躾けられましたが、結局、知識を詰め込んだに過ぎませんでした。
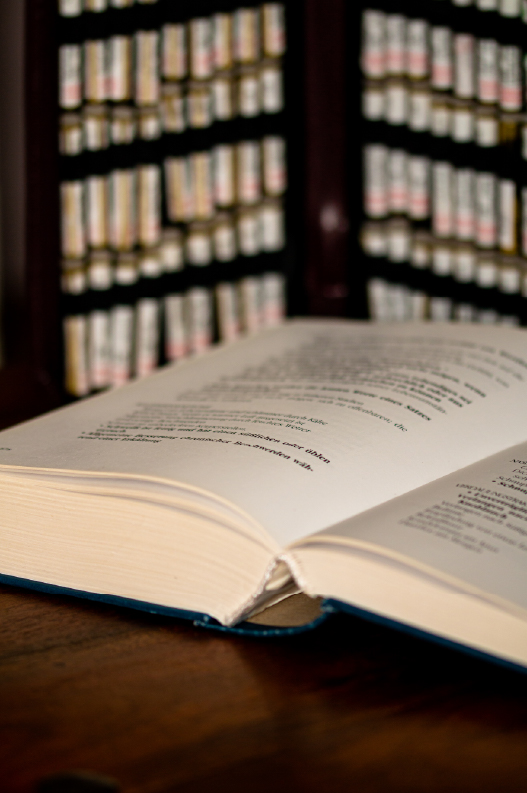 素行はともかく、勉学については抜群の成績をおさめ、ミュラーはとりわけラテン語が得意でした。その後、進学したハレ大学でも、英語、フランス語、ヘブライ語、ギリシャ語など次々と外国語を習得していきました。
素行はともかく、勉学については抜群の成績をおさめ、ミュラーはとりわけラテン語が得意でした。その後、進学したハレ大学でも、英語、フランス語、ヘブライ語、ギリシャ語など次々と外国語を習得していきました。
神学生になっても内面的には何も変わっていませんでしたが、神学の基礎訓練を受け、父の願い通り、ルター派の国教会で説教を行う国家資格を得ます。
ミュラーの日記には、この頃、自分が虚しさや孤独を感じてさ迷い、それまで形式的に扱っていたキリスト教の本質を知りたいという渇望が芽生えていたことが記されています。
そして、小さな家庭集会※に参加したことを機に、ミュラーは文字通り生まれ変わるのです。それは、渇き切った心に湧き出でる泉が与えられたような出来事でした。
※祈りと聖書を学ぶために定期的にクリスチャンが集う場。
1825年11月のある日、学友ベータからの誘いによりワーグナー家で開かれた家庭集会に参加したミュラーは、そこで人生を変える出来事に遭遇します。
次の文章は、その日の出来事についてミュラーが書き残したものです。
跪(ひざまづ)いて祈ることに、私は衝撃を受けた。
なぜなら、彼のように跪いて祈る姿をこれまで見たことがなく、私自身もそうして跪いて祈ったことなどなかったからだ。
それから、彼は聖句と印刷された説教を読み上げた。
叙階された聖職者が出席した場合を除いて、プロイセンでは聖書を釈義する集会は許されていなかったためだ。
集会の終わりに再び賛美歌を歌い、そして最後に家の主人が祈った。
彼が祈っている間、次のように私は思った。
「私はこの無学の男性よりもはるかに学んでいるが、このようには祈ることができない。」
集会全体が実に衝撃的だった。それでいて、私は幸せを感じた。
でも、なぜ幸せなのかと聞かれたら、それにははっきりと答えられなかった。
この静かで素朴な集いに、何か特別な高揚感や神秘的なことがあったわけでもありませんでした。しかし、ミュラーは、人が神の前に跪くその姿勢に衝撃を受け、集いを通して自分にはないものを感じ取ったのです。
ミュラーはこの日の帰り道、以前、一緒にスイスを旅行したこともあったベータに「スイスの旅で見たことやこれまでの喜びすべて、今夜の家庭集会で受けた喜びに比べたら何でもない」と語ったほど感激を受けたのでした。
自分が家に帰って、神に跪いて祈れたかどうかは思い出せない。
しかし、私はベッドの中で平安で幸せに満たされて横たわっていた。
そして、主が様々な方法でその働きを始めているように感じた。
私は心の深い悲しみもなく、ほとんど知識もなく喜びを手に入れたが、その夜、主が私に恵みの働きを始められたことに疑いの余地はなかった。
その夜が、私の人生のターニングポイントだった。
翌日と月曜日、そして週に 1、 2 回、私はこの兄弟の家に行き、そこで彼と別の兄弟と一緒に聖書を読むようになった。
土曜日が来るまで待つには長すぎたのだ。
晩年、海外宣教師として各国に赴いたミュラーは、来日した際の説教でも、この新たに生まれた「誕生日」について語ったと言われています。
ミュラーにとって、自分の魂がイエスと結びつき新たにされた日は、何歳になっても特別な日だったのです。
あなたがたは新しく生れなければならないと、わたしが言ったからとて、不思議に思うには及ばない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞くが、それがどこからきて、どこへ行くかは知らない。霊から生れる者もみな、それと同じである。
(ヨハネによる福音書3章7節~8節)イエスの言葉
ミュラーは、この後亡くなるまでの70年余りを「神に栄光を帰す」ことに命を捧げます。
最初の家庭集会に参加した翌年以降、ミュラーは海外宣教師になる決意を固めていきます。
ところが、キリストに献身したことを喜んでくれると思っていたミュラーの予想に反して、父親は名誉ある国教会の聖職者の職を捨てたことに激怒し、学費や生活費の仕送りを止め、ミュラーを勘当したのです。※
※この後、10年後に父親はミュラーを通して回心し、キリスト者となっています。
苦境に陥ったミュラーは、この時から真剣に神に跪いて祈ることを始めました。
すると、多言語を使いこなすことのできるミュラーに、ハレ大学に客員教授として滞在するアメリカからの神学者の通訳や翻訳をする、補助職務の仕事が舞い込んできたのです。大学からの収入を得ることができたミュラーは、残り2年間の大学生活を不自由なく送ります。
その後、何十年と続く神とミュラーの祈りと応答のはじまりでした。
この頃、ミュラーは自分がフランス語からドイツ語に翻訳した文学書の原稿料を得る契約を結んでいました。しかし、「世俗的なものを出版することは、神の御心ではないのではないか」という疑問が生じ、悩んだ結果、出版契約を破棄して、翻訳原稿をすべて焼き捨ててしまいます。神に出会って以降のミュラーの潔さを感じさせるエピソードです。
 1829年、24歳でミュラーは海外宣教師としてイギリスへ渡ります。
1829年、24歳でミュラーは海外宣教師としてイギリスへ渡ります。
しかし、渡航先で再発した病による深刻な状態が続き、デボンシャー州のティマンスで静養することを余儀なくされます。
このときミュラーは身体的苦しみだけでなく、少年時代からの罪深い生活や、母の死に際しての自分の姿など、過去の罪の意識に苛まれる苦悶も経験します。
そして、この苦しみを通して一層神に頼るようになるのです。
渡航の翌年、ミュラーはティマンスで出会ったメアリー・グローブスと結婚します。新婚生活は凄まじいほどの貧困生活でしたが、その都度、必要なお金が与えられたことが自叙伝に淡々と綴られています。
亡くなるまでの40年間、良きパートナーとしてメアリーはミュラーと二人三脚で働き、特に孤児院運営※における彼女の功績は多大なものでした。
※夫婦によって始められた孤児院事業は、その後、成長した二人の娘リディアへと引き継がれていきました。
1832年は欧州全土でコレラが蔓延し、ミュラーが移り住んだブリストルでも多くの死者が出ていました。
ミュラーは日曜学校の働きの一環として、貧しい子どもたちに路上でパンを配る活動を開始し、その子どもたちに聖書を教えるようになりました。
こういった働きが、孤児院事業の先駆けとなったのです。
1835年、ミュラーは孤児院創設のために祈り続け、とうとう神からの応答を得ます。それは詩篇の次の言葉でした。
わたしはエジプトの国から、あなたをつれ出したあなたの神、主である。
あなたの口を広くあけよ、わたしはそれを満たそう。
(詩篇81篇10節)
当時、ミュラーの全財産は現在の日本円にして約1万3千円でしたが、生涯座右に置いたこの御言葉によって、ミュラーは孤児院事業を進める決意を固めます。
ミュラーは孤児院創設の目的を、次の3つにまとめて趣意書に記載しました。
ミュラーは事業によって神の栄光を現すことを第一とし、その志は最後まで変わりませんでした。そして、人に頼ることなく神のみに頼り、祈ることによって働きを成していくことを貫きました。
最初に、針仕事をしていた婦人から祖母の遺産の約20万円が捧げられ、奉仕を希望する人も続き、1836年に女の子のための孤児院がスタートしました。
その後、男女の幼児を収容する家を創設し、合わせて約30人の子どもたちがそこで生活しました。翌年に第3番目、1853年には第4番目の孤児院が完成し、すべての孤児院を合わせると130人もの孤児が収容されたのです。
 1845年、4つの孤児院でも収容しきれない子どもたちを何とか救いたいと思い、神に祈っていたミュラーに不思議な申し出がありました。
1845年、4つの孤児院でも収容しきれない子どもたちを何とか救いたいと思い、神に祈っていたミュラーに不思議な申し出がありました。
まず、それまでで最高額の献金があったことに続き、ある建築技師の男性が、無報酬で孤児院の設計図を作成し、工事の監督をしたいと申し出て来ました。さらに、子どもたちが運動できる十分な広さを持った土地の地主が、6割の金額でその土地をミュラーに譲り、新しく大きな家を建てる工事を始めることができたのです。
完成した建物は「新しい孤児の家」という名前がつけられました。
1870年には5棟にまで増えた「新しい孤児の家」で、2千人の子どもたちを迎えることができました。
ミュラーは、信仰に基づく人生を生き、また、事業を進めていくために、次の3人の人物の伝記を熟読したと言われています。
フランケは牧師、神学者、教育家で、ミュラーの母校ハレ大学の教授でもあり、ハレに貧民学校、孤児院など多くの学校を創設した人物です。
フランケが建てた孤児院※は、一つの町と言えるほど大規模なものでした。
孤児院の事業を開始して30年間、人に頼らず神にのみ信頼し、自費で経営したフランケの信仰の生き様は、ミュラーに多大な影響を与えました。
※この孤児院では、貧しい神学生のために無料で宿泊施設が開放されており、ミュラーも父からの仕送りが絶たれた際、2カ月ほどこの施設で過ごしたことがありました。
 聖歌「おどろくばかりの(アメージング・グレイス)」を作詞したニュートンは奴隷船の船長でしたが、心を入れ替えて悪事から足を洗い、牧師となって新たな人生を送った人物です。
聖歌「おどろくばかりの(アメージング・グレイス)」を作詞したニュートンは奴隷船の船長でしたが、心を入れ替えて悪事から足を洗い、牧師となって新たな人生を送った人物です。
過去の後悔や自責の念が押し寄せることがあっても、ミュラーは神の言葉を選び、自己卑下という自我への固執を捨て、信仰による新しい人生の歩みを決して止めませんでした。
キリストによって神のものとされた者として生きるニュートンの姿に、ミュラーも励まされたのかもしれません。
不品行な者、偶像を礼拝する者、姦淫をする者、男娼となる者、男色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は、いずれも神の国をつぐことはないのである。あなたがたの中には、以前はそんな人もいた。
しかし、あなたがたは、主イエス・キリストの名によって、またわたしたちの神の霊によって、洗われ、きよめられ、義とされたのである。…(略)…
あなたがたは、代価を払って買いとられたのだ。
それだから、自分のからだをもって、神の栄光をあらわしなさい。
(コリント人への第一の手紙6章9~20節)
 ミュラーは「祈りの人」と呼ばれるほど神に祈りを捧げた人でしたが、その習慣を教えてくれた人物がホイットフィールドでした。
ミュラーは「祈りの人」と呼ばれるほど神に祈りを捧げた人でしたが、その習慣を教えてくれた人物がホイットフィールドでした。
イギリスのメソジスト教会の伝道者であるホイットフィールドは、ウェスレー兄弟の影響を受けて一緒に北アメリカへ渡りました。その後、孤児院を創設し、イギリスとアメリカの教会に大きな影響を与えました。
深い祈りを捧げるとともに、跪いて聖書を読んでいたホイットフィールドの習慣に習って、ミュラーも跪いて聖書を読むようになったと言われています。
その聖なるすまいにおられる神はみなしごの父、やもめの保護者である。
(詩篇68篇5節)
跪いて聖書を読んでいるときにミュラーが出会ったこの言葉は、孤児院事業の基盤となりました。
この言葉に現わされている神の憐みと情け深さを、ミュラーは事業を通して世に示し続けたのです。
1875年、70歳のミュラーは娘夫婦に孤児院事業を委ね、クリスチャンになったばかりの頃の夢であった宣教師としての働きを始めます。
ミュラーは、神が望まれるのであれば「招かれるところどこへでも行く」というシンプルな宣教精神によって、17年間に42カ国を訪問し、6千回の説教を行って3百万人以上の人々にイエス・キリストの福音を語りました。
その足跡は20万マイル(約地球8周)に及びました。
ミュラーは日本にも二度訪れており、日本の社会事業の先駆者である石井十次※や同志社大学の創設者新島襄などの人物にも多大な影響を残しました。
※ミュラーに学んだ石井は、まだ世間が社会福祉に関心を持っていなかった時代に、苦境のなかで日本初の孤児院を創設しました。石井は生涯で3千人の孤児の父となりました。
 87歳のときに宣教旅行を終えたミュラーは、長年、孤児と共に暮らしたブリストルで余生を送りました。
87歳のときに宣教旅行を終えたミュラーは、長年、孤児と共に暮らしたブリストルで余生を送りました。
そして、60年間、牧師として働いたベテスダ教会で最後の最後まで伝道のために働き、亡くなる一週間前まで説教をし、いつものようにベッドの傍で跪いて祈っている最中に天に召されました。ベッドの上には開かれた聖書が置かれていました。
ミュラーは「私が信仰を捨てない限り、神には制限がなく、何度でも満たすことができる。今日救いたもう主は何年後でも救われる」と語り、93年間の地上での生涯を全うしました。
それは、神にのみ頼り、絶えず祈り、神の言葉を信じ握りしめた人生の軌跡でした。
いかがでしたでしょうか。
罪に縛られ支配されていた自分に新しい命を与え、生かしてくださったキリストに全てを捧げたミュラーは、自分ではなく神が讃えられることを望んでいました。
多くの孤児を救済し、世界中の人々を救いに導いたミュラーの生涯は、その願い通りに、今もイエス・キリストを信じる素晴らしさを証ししているのです。
一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。
しかし、もし死んだなら、豊かに実を結ぶようになる。
(ヨハネによる福音書12章24節)
参考文献
『ジョージ・ミュラー 信仰』ランス・ワベルズ(編)、いのちのことば社
『世界の孤児院の父 ジョージ・ミュラー』玉木功、教会新報社
『ジョージ・ミュラーの青年時代の迷走と回心』木原活信、論文
●こちらの記事もどうぞ
Copyright © 新生宣教団 All rights reserved.