
こんにちはTaroです。
皆さんは、「時は金なり」という言葉をご存知ですか。そうベンジャミン・フランクリンの有名な言葉ですよね。「時間を無駄にしてはいけないよ」「時間を無駄にすると損することになるよ」と、自分も子どもの頃から幾度となく聞かされてきたような気がします。
現代の日本人にさえ染み付いているこの考え方は、資本主義的な考え方の素地にもなっていると言われていますが、その資本主義的な考え方に影響を与えたのは「プロテスタント信仰」ではないかと考えた人物がいます。それはマックス・ウェーバー(ヴェーバー)というドイツ人です。
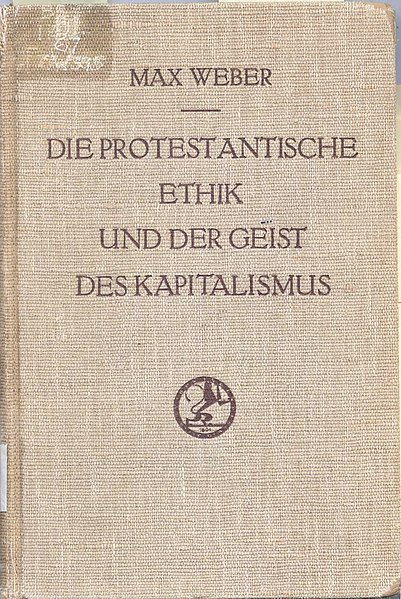 今日はこのマックス・ウェーバーが著した『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』という論文をご紹介しようと思います。とても難しい本なのですが、論点が大変ユニークですし、またどこか読者に自らを顧みる気持ちをおこさせるようで、出版から120年近く過ぎた今でも読みつがれています。一体この論文のどこにそんな魅力があるのかご一緒に見ていきましょう。
今日はこのマックス・ウェーバーが著した『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』という論文をご紹介しようと思います。とても難しい本なのですが、論点が大変ユニークですし、またどこか読者に自らを顧みる気持ちをおこさせるようで、出版から120年近く過ぎた今でも読みつがれています。一体この論文のどこにそんな魅力があるのかご一緒に見ていきましょう。
目次

プロテスタント教会の信徒で新生宣教団の職員。前職から印刷に関わり活版印刷の最後の時代を知る。 趣味は読書(歴史や民俗学関係中心)。明治・江戸の世界が垣間見える寄席好き。カレー愛好者でインド・ネパールから松屋のカレーまでその守備範囲は広い。
ざっくりとした紹介にすぎないとしても、普段聞き慣れない言葉が多用されているので、本題に入るまえにキーワードなど簡単に見てみたいと思います。
著者のマックス・ウェーバーは、1864年にドイツ(プロイセン王国)で、ビスマルク派の政治家の父と、敬虔なプロテスタント(フランスのカルヴィニストの末裔)富裕層家系の母との間に生まれた社会学者、政治学者、経済史学者です。早熟の天才と言われ12歳の時にはマキャベリの『君主論』を読みこなしていたとか。両親は価値観の違いから仲が悪かったらしく、その緊張感の中で育ったことが、政治と宗教の原理的対立を突き詰めて考える彼の基本姿勢につながったとも言われています。
彼はベルリン大学で学んだ時期があるのですが、その2年前に、彼が師事した教授に伊藤博文が憲法を学びにきていたのだとか。彼が生きていたのはそんな時代です。
後にウェーバーはハイデルベルク大学の教授になりますが、『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』は、父親との確執によって神経を病んで大学を休職し、その回復まもない1904-1905年に著されました。この『プロ倫』(略称)は飛び抜けて注目度が高いのですが、彼の論文の一つに過ぎず、比較宗教社会学では『儒教と道教』、『ヒンドゥー教と仏教』、『古代ユダヤ教』を著したり、『職業としての学問』、『職業としての政治』などの講演が書籍になっています。1920年、当時大流行したスペイン風邪により56歳の若さで亡くなりました。
そもそも資本主義とは何でしょうか。広い意味では「永続的な金儲けの営み」、「ある程度組織的に行われる金儲け」のことを指し、ウェーバーは、商業であろうと金貸しであろうとその他何であろうと、暴力を伴わない経済的営みであれば、そういうものすべてを「資本主義」と呼んでいるようです(389p参照)。そしてそれは、古代ギリシャ、ローマはもとより、インド、中国や西アジアなどでも古くから見られるものであったといいます。(45p、379~382p参照)
一方、彼が本書のメインテーマである「資本主義の精神」というときの資本主義とは、現代につながる「経営的な、産業経営的な資本主義」、「近代資本主義」のことを指しています。資本家が設備や労働を集約して利益を産み出し、それを拡大させていく営みのことです。
もう一つのテーマはプロテスタントです。カトリックとプロテスタントの違いについてこのコーナーの別な記事で丁寧に解説していますから、こちらを御覧ください。
ポイントだけお伝えしますと、1517年にマルチン・ルターがローマ・カトリック教会に対して、『95か条の論題』を提示したことにより始まったとされます。それは、教会が魂の救いを『免罪符』販売という形で提供していたことに対する抗議で、「神の義」(救い)は人の善行や努力、ましてや金で買うことなどできるものではなく、人が救われるのはただ「神の恵み」によるのであり、それを信じる信仰によってのみ「義」とされると主張しました。
以降、カトリックに対するプロテスタント(抗議する者)として分離して、誰もが読めるように現地言語による聖書翻訳や、教会の典礼を洗礼と聖餐のみにするなどの改革を行い、救いが人の行いによって得られるものでは無いことを明確にしていきました。
宗教改革初期の指導者の一人、フランス人神学者ジャン・カルヴァン(カルバン)の神学・思想を表します。
カルヴァンの神学では、神の絶対性、聖書の権威、教会政治、信徒生活の訓練などが強調され、とりわけ「人の救いは予(あらかじ)め神によって運命づけられている」とする『予定説(二重予定説)』は神の絶対性を突き詰めた特徴的な教えといえます。カルヴァンの教えは教派を超えてプロテスタント諸派に影響を与えたと言われ、特にフランス、オランダ、イギリス、アメリカへと広がりました。
大まかに言うと、イギリスのカルヴァン派と、そこから派生した諸派(メソジスト、バプテスト、敬虔派など)の人たちを指します。彼らは、厳格、清潔、清貧を旨としたため、日本語では『清教徒』と訳されています。
ルイ14世によるナントの勅令廃止によってフランスから逃げ延びてきたカルヴァン派信徒が、イギリスに根付いて中産階級(ジェントリ)になり、イギリス議会でも有力な議員になっていきました。
17世紀半ばのイギリスは絶対王政下にあり、国王は英国国教会の首長でもありました。国教会による教義や制度の強要、国王による大商人への独占的利権乱発などの問題なども絡み合って、国王と議会の間に対立が生まれていきます。信仰の自由を求める運動や、王政の改革を求める運動が生まれ、ピルグリム・ファーザーズ(※)の北米移住の動きや、清教徒革命にも発展していきました。
この国教会の改革を求め、制度批判を行ったカルヴァン派とまつわる諸派の人々がピューリタンと呼ばれ、この人々の印象が、「プロテスタント」は禁欲主義者というイメージに繋がっているのかも知れませんね。
ウェーバーが語っている「禁欲」の意味については、本題で見ていきましょう。
※ピルグリム・ファーザーズ:国教会を強制するジェームズ1世の迫害から逃れ、メイフラワー号に乗って北アメリカに渡った、イングランドのピューリタンたち。
「時は金なり」は、冒頭で述べたように、アメリカ建国の父と言われるベンジャミン・フランクリンの言葉です。
彼は、アメリカ独立戦争の指導者の1人であり、独立宣言の起草委員にして、最初に署名した5人の議員の1人でした。その他、郵政関係での功績や、ペンシルベニア大学の創立、雷や竜巻のメカニズム解明や、様々な発明も行い、84年の生涯は大変密度の高いものだったと言えます。
「時は金なり」は彼が1748年に著した『老人から若い商人への忠告』という文章の中の言葉で、本来の意味は「機会損失」を戒めるもので経済活動に直結する内容です。
ただ一方で彼は、「道徳的完全に到達する大胆で難儀な計画」を思いついたとして、13の徳目(節制・沈黙・規律・勤勉・清潔・謙譲など)をまとめ、自ら週1つずつを4回実践していたこともあり、「時は金なり」は「時間はお金に匹敵するほど大切なもの」と広く解釈されることが多くなったようです。
彼が活躍した時代は、ピルグリム・ファーザーズのアメリカ到着から150年ほど後ですが、その基盤はピューリタンの精神そのものと言えるかもしれません。もっとも、すでにその信仰は薄れてきていたとも指摘されています。
本文には度々、「エートス」という言葉が出てきます。語源はehtos(ethos)というギリシア語で、「道徳」とか「習俗」を示す言葉だそうです。社会学においてよく使われるようになったのはマックス・ウェーバーが使い出してからのようですが、彼はこの言葉をどのような意味で使っているのでしょうか。
それは「ある地域で歴史的に人々が身につけた共通する価値観や倫理的雰囲気」といったもので、平たく言うと「その社会が共有する道徳的心情」と言えるのではないかと思います。これは外圧的なものではなく、内発的、自由意志により行動となって現れるものを指します。
マックス・ウェーバーが、社会を科学する捉え方にこのエートスという概念をもってきたことは画期的といわれています。確かに、人々の社会ですので、その社会の構成員の根底にある倫理や意識がそれを成り立たせていると考えるのは自然なことなのかも知れません。
それでは、本題に入りましょう。
まず彼が着目したのは、統計的に比較するに、カトリック信徒は手工業にとどまる一方、資本所有や経営者、高級労働に関わりを持とうとしたのはプロテスタント信徒が圧倒的に多く、また子どもの教育(学校の選択)にもその傾向が見られるという事実でした。しかもそれは、オランダ、イギリス、フランス、アメリカなどカルヴィニズムが優勢な地域だというのです。
それから、宗教改革の結果、人々の生活に対する教会の支配はなくなったのではなく、かえって別な支配に変えたのだと説明します。つまり、カトリック教会における支配は楽なものだったのに、新たにもたらされたプロテスタント教会による支配は厄介な規律を人々に要求するものだったとのことです。(17p参)
つづいてウェーバーは、資本主義の「精神」という言葉に触れ、エートスという考え方を説明していきます。
そこで、取り上げたのがベンジャミン・フランクリンの「時は金なり」の一節でした。一見利己主義に走っていると思えるその内容の背後に、「個人的な金儲けや享楽主義」というより、むしろ職業義務に忠実な人々の姿を見て取っています。(47p参)
また、労働者の資質の高さが、生産性を上げ資本主義を発達させるのに不可欠であることにも注目しています。それは、伝統主義では労働者は「できるだけ多く労働すればどれだけ報酬が得られるか、ではなくて、従来の報酬を得られるためにはどれだけ労働しなければならないかという発想にとどまる」のに対し、高度な製品の製造に携わる労働者の場合には、「あたかも労働が絶対的な自己目的-天職Beruf(ベルーフ)-であるかのように励む」(67p)という心情が必要になると語っています。
ここで、「利潤追求の営み(資本主義)」と相反すると思われる「信仰による生き方」が資本主義の発展に実は作用しているのではとの考察が始まるのです。逆に言うと、当時興隆していた中産的生産者層が、厳格で金儲けに否定的な筈のカルヴァン主義信仰を喜んで受け入れ、擁護していった背景には何があるのかに目を向けていくのです。
 そこで、「天職:Beruf/Calling」(独語:ベルーフ/英語:コーリング)という意識がどのように近代資本主義の担い手たちの内側に芽生えてきたのかを考えます。
そこで、「天職:Beruf/Calling」(独語:ベルーフ/英語:コーリング)という意識がどのように近代資本主義の担い手たちの内側に芽生えてきたのかを考えます。
そもそも、職業に神の思し召しがあるという考え方は一般的ではありませんでした。これは、宗教改革者ルターが、自国語で誰もが聖書を読めるようにと翻訳を始めていく中で、初めて持ち込んだ概念と言われています。当時「Beruf」という言葉には「神の思し召し」、「召命」の意味はありましたが、「職業」という意味はなく、ルターはその「Beruf」を現在一般的につかわれている「職業」にも当てたのです。
ルターが意識したのは、「何も修道院のような特別な場所のみに神の思し召しが働いているのではない。むしろ世俗的な日常労働の中にも神の召しは働いていて、日常生活に忠実であることは隣人愛の実践であり、修道院で神に仕えること以上に尊いのだ」ということでした。それは個人個人が教会や聖職者を介さず、直(じか)に神と向き合うことができるし、そうある筈だという考えに基づいています。
それは重要なポイントになったのですが、ルター自身は資本主義の発展につながるような意識を持つことはなく、職業生活への態度においては伝統主義の枠から出ることはなかったようです。つまり「神の召しなので、甘受し、適従し、変わることなくそこにとどまり続けるべき」といったような固定化した意識ですね。
※ちなみに、本書の日本語訳を行った大塚久雄氏は、神の意志によるという意味も含ませるためにウェーバーが論ずる「Beruf」を「天職」と訳出されました。
近代資本主義の発展が目覚ましかった、オランダ、イギリス、フランスなどに目を向けるとき、そこがカルヴィニズムの盛んな地域であることに注目しています。
カルヴァンの教えはそれが全てでは無いけれども、特徴的な教理に「予定説」というものがあります。先に述べたように、人が救われるのは、神の一方的な恵みによるものであって、人の側(地上の教会も含む)の一切の努力は無意味であるというものです。始めから神は誰を救って誰を救わないか決めている(その権威がある)と言うのです。
そのことは、個々人に「内面的孤独化の感情」(156p)をもたらしました。「自分は果たして神の選びに与っているのだろうか」という思いですね。その結果人々は自暴自棄になったのでしょうか。
ところが実際はそうではありませんでした。
「自分が救われ、神の国に入るために努力することは無意味であるが、神の御心を行い、その結果繁栄が与えられるならば、社会にも隣人にも愛を示すことになり、神の栄光をあらわすことになる。つまりはそのことが選びを裏付けていることになるのだ」ということで、その意識が生活態度にも、仕事に向かう姿勢にも現れてきたのです。つまり、安心の拠り所となったということですね。
これが、プロテスタントが禁欲的だと言われるようになった由縁(ゆえん)ではないでしょうか。つまり、修道院のような特殊な場所ではなくて、日常の生活や労働の中に節制や誠実、勤勉や規律などを探求する姿勢がプロテスタンティズムの中に現れてきたということでした。禁欲と言っても自らに難行苦行を課したり、物断ちをするというようなことではなく、生活の中でいかに神の栄光をあらわすかという能動的、自発的なものだったようです。そして、後にカルヴァン派を中心にピューリタン(清貧なる者)と呼ばれる人々が現れてきます。
プロテスタンティズムの世俗内禁欲は、どのような方向へ行ったのでしょうか。
「彼らは、所有物の享楽的、奢侈(しゃし)的な消費を圧殺した一方で、財の獲得そのものについては伝統主義的倫理の障害から解き放ち、利潤追求は神の意志に沿うものとして合法化した。(342p参)」とあります。
つまり、金儲けを享楽の手段とするのは神の意志に反するものだが、その富を有益に用いることは天職義務に忠実なことと考えたのですね。
また、富の活用だけではなく、時間の活用にも同等以上の注意を払いました。「時間を無駄にすることは、神に与えられた善を行う機会を活かさない罪深いことだ」と。
このピューリタンの禁欲的な生き方(エートス)は、たゆまぬ努力を産み、また努力の中で富が蓄積され、その富は再投資に用いられ、その結果ますます拡大していくという、近代資本主義の合理主義にマッチしたばかりか、推進力、梃子(てこ)の働きをしていったと分析しています。
古くからオリエント(中国やインド、西アジア)に見られた資本主義が、比較的制約を受けない自由な考え方の内にあったのにも関わらず近代資本主義へと発展しなかったのに対し、金儲けには厳しい目がむけられていたカルヴィニズムの諸地域でそれが発展したのには、自由気ままに利を貪ることを善しとしない自制心というものが働いていたことも重要な要素だったと言われます。適正利潤という考え方がそのしくみを安定的にしたということです。
さて、近代資本主義がそのように発展、構築されていった結果、今度は資本主義のしくみそのものが、その制度にマッチした「禁欲的で合理的な生活態度」を人々に強要するようになりました。
この否応なしに強制力をもってくる資本主義の外枠のことをウェーバーは「鉄の檻」という言葉で表していますが、この「鉄の檻」から世俗内的禁欲とか天職義務といった「精神」(内面性)は抜け出てしまい、機械の基礎の上に立った資本主義はこの支柱(精神)を必要としなくなったのだといいます。
営利活動は宗教的・倫理的意味を取り去られ、それはルールを守ってハイスコアを争うスポーツのようでもあるというのです。(366p参)
つまりは、資本主義の社会的機構は、その存続発展のために必要な姿勢や態度をこれまで同様に人々に求めてくるが、その内発的動機については問わなくなるということなのでしょう。当然、合理的であることや、時間を無駄にせず、信用を重視し、絶えず成長を続けるといった経営や労働のあり方は重要であり、そういった徳目を無視して存続は厳しいと思うのです。しかし、どういう思いで取り組むのかは関係が無くなり、営利活動(資本主義の社会的機構の存続発展)自体が目的になり、姿勢や徳目はその手段になってきつつあることを指摘しています。
最後に、ウェーバーがこの論文の最後の方で語った有名な一節をそのまま記載します。
……将来この鉄の檻の中に住むものは誰なのか、そして、この巨大な発展が終わるとき、まったく新しい預言者たちが現れるのか、あるいはかつての思想や理想の力強い復活が起こるのか、それとも ――そのどちらでもなくて――一種の異常な尊大さで粉飾された機械的化石と化することになるのか、まだ誰も分からない。それはそれとして、こうした文化発展の最後に現れる「末人たち」(letzte Menschen)にとっては、次の言葉が真理となるのではなかろうか。「精神のない専門人、心情のない享楽人。この無のもの(Nichts)は、人間性のかつて達したことのない段階にまですでに登りつめた、と自惚れるだろう」と。(366p)
駆け足で『プロ倫』を見てきましたがいかがでしたか。
マックス・ウェーバーはプロテスタントが資本主義を興したとか、それを目指したなどということは全く言っていません。彼はただ、ある地域のプロテスタント信仰が資本主義の発展に大きく影響したということを指摘していて、それは一つの要因として確かに十分にあり得ることかと思いました。「禁欲」という「金儲け」とは真逆の態度が、金儲けの仕組みを建て上げる一つの原動力になったというのは面白いですね。そしてその仕組みそのものがある意味独り歩きを始めたのではないかと思われる指摘にも考えさせられるものがありました。
この論文が最初に発表されたのが1904-5年とされていますから、120年近く経とうとしています。AIとかロボットの社会進出や、企業の不正問題が世間を騒がせている今、働くことの意味が改めて問われています。「鉄の檻」とか「精神のない専門人、心情のない享楽人」などの言葉は、皆さんにはどのよう感じられたでしょうか。
働く目的が明確で「これが天職だ」と思って働くことが良いこととわかっていても、それが見えにくくなっている現在、私たちの働くことのモチベーションはどこにあるでしょうか。
本書が今でも読み続けられている理由は、著者の意図するところとは外れるとは思うのですが、ひょっとすると、私たちに、今の社会と自分自身の働く意味を見比べてもう一度考えさせてくれるところにあるのかもしれませんね。
ここでのご紹介は全く不十分なもの。皆さんも是非一度お読みになってみてください。
そして、聖書から生きる意味そのものについて思い巡らせてみるのも良いかもしれません。
では。
Taro
わたしたちは神の作品であって、良い行いをするように、キリスト・イエスにあって造られたのである。神は、わたしたちが、良い行いをして日を過ごすようにと、あらかじめ備えて下さったのである。
エペソ人への手紙 2:10
引用文献:
プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神(マックス・ウェーバー著/大塚久雄訳)岩波文庫
参考文献:
マックス・ウェーバー 近代と格闘した思想家(野口雅弘著)中公新書
プロテスタンティズム 宗教改革から現代政治まで(深井智朗著)中公新書
ウエストミンスター信仰告白(日本キリスト改革派教会訳)ウェブサイト
●こちらの記事もおすすめ
Copyright © 新生宣教団 All rights reserved.